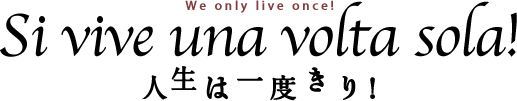わたしは兼業農家での暮らしにきわめて満足しているが、ふと経済的にどうなのか気になって、亭主殿にウチの稲作の収支について尋ねてみた。
自家用を除き、農協への出荷と知人に売る分が23万円。これが去年の唯一の収入だ。
支出は農協から買う苗が4万、農薬や肥料が6万、稲刈り後のもみ殻の除去と玄米の乾燥代に4万、農業機械の点検が最低10万、計24万円で、すでに赤字。水管理や耕作、草刈り、稲刈りなどの作業は、まったくのタダ働き。かなりの重労働なのだが。
それでも、亡父がトラクター、田植え機、コンバインという機械を退職金で買ってくれていたからこそ、ウチは稲作を続けていられるが、もし3台新品を買うとなると500万は優に超え、故障すればこれまた3、40万すぐ飛ぶ。政府は農業の機械化を言うが、田植え機を使うのは1年間にたった1日、稲刈り用のコンバインで2日、トラクターでも6日。農業機械は値段が高いわりに、投資効率がお話にならないほど悪いのだ。
「農業は趣味だ」と亭主殿は笑って断言する。「もうけを考えたらやっていけないよ」
亭主殿には農家の跡取りという自覚があるから納得して稲作を続けているが、都会に住む子どもたちの代になった時、「損になっても稲作をしてくれ」とは、とても言えない。
では他人に頼むか?
近所に農業法人があり、稲作を請け負う。が、田んぼの持ち主は請負い賃を払わなければならず、できた米はすべて法人のもので、持ち主側が希望すれば市場価格より安く買えるらしい。これなら、米をつくらず耕作放棄地にするほうが損にならない。
日本の米生産の未来を考えると、安価な農業機械を開発し、もうかる稲作にすることが欠かせないと強く思う。