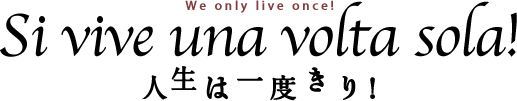わたしは医学・薬学領域の和英翻訳を主な仕事にしているが、この1年半ほどでオファーが激減し、収入の大半が消えた。
理由はAI(人工知能)の進歩。
AIのおかげで失業数が増えるとの予測は新聞で読んでいたが、まさかこの自分が、しかもこんなに早く失業するとは思ってもみなかった。
コンピュータの翻訳ソフトは10年以上前からあった。しかし正確さに欠け、単語ならまだしも文章となるとお話にならなかった。それがこの1、2年、グーグルの翻訳がかなり使い物になる。仕事で自分が難儀する時に試してみると、「その手があったか」という訳が出てくる。
スマホでも、翻訳アプリが無料で使える。イギリス人と話した友人によると、「僕、英語はてんでダメなんですけど、日本語でスマホに話しかけたら英語が表示されて、相手の話す英語は日本語に変換されるから、ずっとコミュニケーションできたんですよ。ただし、それは一定期間だけで、それを過ぎると翻訳の質がガタ落ちして、使えなくなりました」。
これは無料アプリの場合で、有料の翻訳ソフトならずっと質が高いままだ。しかも、企業が過去の和英対訳の文書を大量にデータ処理すれば、さらに正確度が上がり、人間の訳文と同等だろう。
人間とAIの翻訳の一番の違いは所要時間で、人間が20時間かけて訳すところが、AIなら20分かからないだろう。これでは人間の翻訳屋の出番はない。
あーあ、翻訳はわたしの天職だと思っていたのになぁ……。ボケなければ80歳まで翻訳で稼げる筈だったのに。
誰しも時代の変化には勝てない。家電量販店が増えてから、町の電器屋さんは商売あがったりになったのと同じだ。今からどうするか、悩ましい日々である。