今年の春、例年どおり「筍掘りプロジェクト」を4回計画した。街中住まいで山に入る機会が滅多にない人に、筍掘りを楽しんでもらう目的だ。
ところが4月初めにウチの筍山に行ってみると、肝心の筍が1本も出ていない。2、3年前からこの山に生える筍の数がどうも減っているようだと思っていたのだが、ついに大量の孟宗竹(もうそうちく)が枯れてしまっていた。代わりに親戚の管理する土地に筍が山ほど出ていたので、あわてて場所を変え、プロジェクトはなんとか格好がついた。
竹が枯れているのはウチの山だけではなく、あっちでもこっちでも葉が茶色に枯れて、幹だけになった孟宗竹がたくさん見える。
そういえば去年と一昨年はあちこちで竹の花が咲いていた。竹はまっすぐな幹から節ごとに枝が出て葉が茂るが、ふだんは見かけない小枝の束がそこに混じり、稲の花に似た小さな花がつく(竹はイネ科なんですね)。こりゃ竹が枯れる、と思っていたら案の定だった。
筍がとれる太い孟宗竹は、60年に一度花が咲き、地下茎でつながっている一群の竹がすべて枯れるという。
60年に一度なら、人間の一生に一度しか見られない。こんな長いスパンの「栄枯盛衰」があるなんて、自然は実におもしろいね。花が咲くからには種ができる筈で、その種から新しい竹が生え、再び竹藪が育つ。
ちょうど「竹藪の一生」の終わりと再生を、わたしたちは見ているのだ。
最近はどこもかしこも竹藪だらけになっていたのが、これで竹が減ってエエこっちゃ、と喜んでいたら、何のことはない、6月になると青々とした竹がちゃんと増えている。少々暑くなろうがお構いなし。よほど土地などの条件が竹に合っているのだろう。
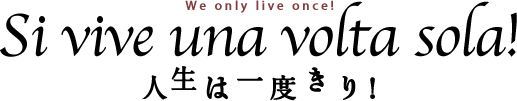


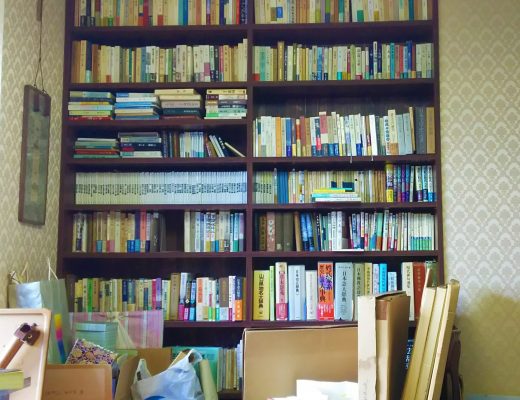

No Comments